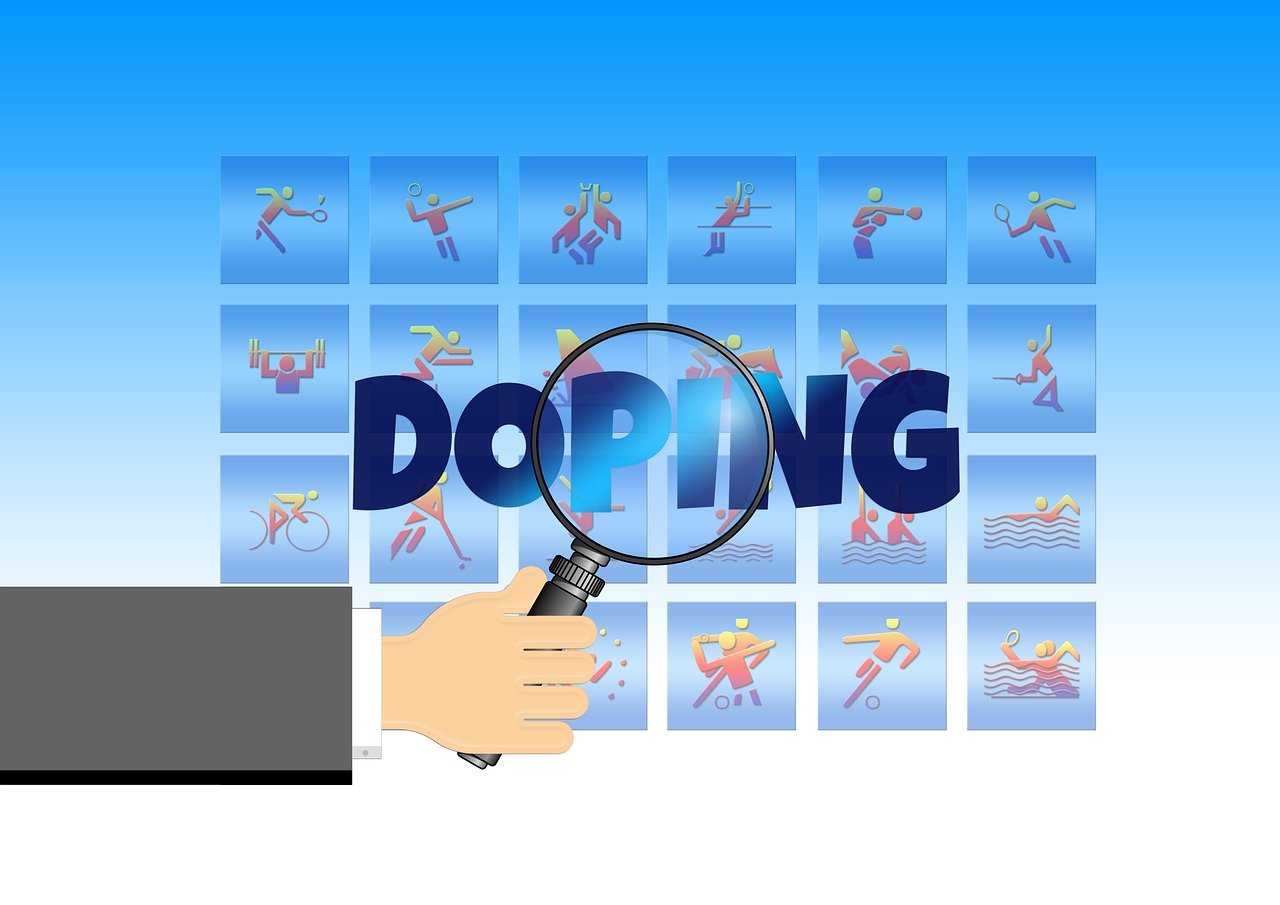1.ポリファーマシーとは? ―「薬の飲みすぎ」が問題になる理由
高齢者の健康管理で注目されるキーワードのひとつが「ポリファーマシー(polypharmacy)」です。直訳すると「多剤併用」を意味しますが、近年では「薬の飲みすぎによる健康への悪影響」というニュアンスで使われることが多くなっています。
例えば、糖尿病・高血圧・脂質異常症・骨粗しょう症など複数の慢性疾患を抱える高齢者は、自然と薬の数が増えがちです。しかし薬が増えるほど、副作用や薬同士の相互作用、服薬ミスなどのリスクが高まり、逆に健康を害してしまう可能性も出てきます。
厚生労働省もポリファーマシーを課題と認識しており、医療費の増加や患者のQOL(生活の質)低下を防ぐために、全国的な対策が進められています[1]。
2.ポリファーマシーの定義 ―何種類からが「多すぎ」なのか?
● 薬の数による定義
一般的には「5剤以上の薬を定期的に内服している状態」がポリファーマシーと定義されることが多いです。ただしこれはあくまで目安であり、「薬の数ではなく、必要性や有効性の観点が重要」とする見解もあります。
🔎 日本老年医学会は、ポリファーマシーを「薬剤数が多く、有害事象や服薬アドヒアランスの低下などの問題を引き起こす状態」と定義しています[2]。
● 必要な薬が多い場合もある
誤解してはいけないのは、「多剤=悪」ではないということ。心不全や糖尿病など、複数の薬を組み合わせることで効果を発揮する病気もあるため、あくまで“不必要な多剤併用”が問題なのです。
3.ポリファーマシーのリスク ―何がそんなに問題なのか?
ポリファーマシーは、以下のようなリスクを引き起こす可能性があります。
① 副作用や薬物相互作用のリスク増加
薬が増えると、副作用の頻度が上がるだけでなく、薬同士が互いに悪影響を及ぼす「相互作用」**も生じやすくなります。ある薬が他の薬の効果を強めたり弱めたりすることで、思わぬ健康トラブルにつながることも。
② 転倒・せん妄・認知機能の低下
高齢者では特にふらつき、めまい、混乱、せん妄などが出現しやすくなります。これにより、転倒や骨折のリスクが高まるという研究結果も多数報告されています[3]。
③ 医療費の無駄・受診回数の増加
不要な薬が処方され続けることで、医療費や薬剤費が無駄に増える可能性があります。また、薬の副作用によって新たな病状が出現し、受診回数が増える悪循環も起こりえます。
④ 服薬ミスの増加
種類が多くなると飲み忘れ・飲み間違いが増え、結果的に治療効果が薄れるどころか、危険な状態に陥ることもあります。
4.ポリファーマシーの評価方法 ―どうやって見つけて、どう対処する?
医療現場では、ポリファーマシーを評価・見直すためのツールがいくつか使用されています。
● お薬手帳の活用
すべての薬局や医療機関で一元管理できるよう、「お薬手帳」を活用しましょう。複数の医師・診療科を受診している場合も、一冊にまとめておくことで重複や相互作用の確認が可能になります。
● STOPP/START基準(高齢者適正処方の国際的ガイドライン)
-
STOPP:中止すべき薬を評価
-
START:新たに必要な薬を評価
特に高齢者の薬剤評価に有効で、ヨーロッパで広く活用されています[4]。
● Beers Criteria(米国老年医学会)
高齢者にとってリスクの高い薬をリスト化したガイドラインで、日本の臨床現場でも参考にされることが増えています。
5.ポリファーマシーにならないために ―今日からできる対策5選
① かかりつけ医・かかりつけ薬局を持つ
複数の診療科にかかっていても、薬の全体像を一人の医師・薬剤師が把握していることが重要です。
② 定期的に薬の棚卸し(レビュー)をする
半年~1年ごとに「今飲んでいる薬が本当に必要か?」を医療者と一緒に見直しましょう。
③ 市販薬やサプリも医師に報告
実は、市販薬や健康食品、漢方薬との飲み合わせがトラブルの原因になることもあります。隠さず相談しましょう。
④ 薬の目的を自分で把握する
「なぜこの薬を飲んでいるのか?」を自分で説明できるようにすると、不要な薬の発見にもつながります。
⑤ 減薬の提案は遠慮せずに
「薬を減らせませんか?」と医師に相談することは、患者として当然の権利です。遠慮せずに伝えましょう。
6.「必要なポリファーマシー」もある ―すべてが悪ではない!
ポリファーマシーという言葉にはネガティブな印象がありますが、すべてが「悪」ではありません。
● 適正な多剤併用は「適正ポリファーマシー」
たとえば心不全では、β遮断薬・利尿薬・ACE阻害薬などを併用することが推奨されており、これはエビデンスに基づく「適正ポリファーマシー」です。
✔︎重要なのは、「一人ひとりに合わせた最小限で最大効果のある処方」です。
7.まとめ ―薬と正しく付き合い、健康寿命をのばそう
ポリファーマシーは、加齢に伴う病気の増加により避けがたい問題かもしれません。しかし、薬の使い方を工夫し、定期的に見直すことで健康を守ることが可能です。
✔︎覚えておきたいポイント
- ポリファーマシーは「必要以上の薬の併用」
- 副作用や転倒、認知症のリスクが高まる
- 見直しはかかりつけ医・薬剤師と協力して
- 減薬は“悪いこと”ではない、健康管理の一環
自分や家族の薬の見直し、今こそ始めてみませんか?
参考文献
- 厚生労働省. 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)2021年版.
https://www.mhlw.go.jp/content/000791064.pdf - 日本老年医学会. 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2021.
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20210922_01.pdf - Kojima G, et al. (2012). Association of polypharmacy with fall risk among older adults: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 60(12):2221–2228. https://doi.org/10.1111/jgs.12074
- O’Mahony D, et al. (2015). STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age and Ageing, 44(2):213–218.
https://doi.org/10.1093/ageing/afu145 - American Geriatrics Society. (2019). Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 67(4):674–694. https://doi.org/10.1111/jgs.15767
- 佐々木英忠, 村田和彦. ポリファーマシーに関する現状と課題. 日本医事新報, 2018年